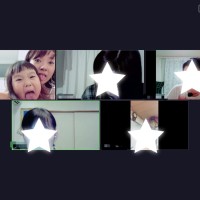私が憧れている女性は、
みんな美人。
というか、
顔の造形にかかわらず、美人として生きている。
もちろん、顔の作りが良いに越したことはない!
けど、仮にそうじゃなくても、
私は美人です♡というオーラで生きている。
私もそのオーラをまといたい!!!!!
と、人生ではじめて思っている最近。
私、美しくなりたい気持ちは無くはないけれど
基本的に昔から美はかなり後回し。
それで困ったこともなくて、
むしろ、今のこの「地味で適度にブス」を生きることで
すごいメリットを享受して生きてきました・・!
そのせいか、これまで、
美人になる覚悟が全然できてなかった。
まず「地味」について。
たとえば学生時代、この地味な容姿ですごい得をしてきました。
同じスカートの丈で通学していても、
派手で可愛い子は怒られて、
地味な私は怒られなかったり。笑
これ、ウソのようなホントの話。
何か人と違うことをしたときにも
目立たないので怒られない!
まぁ同時に、
事業をやっていたりすると、目立たないのはデメリットでもあるんですけどね。
次に、「適度にブス」について、
私の分析によると、「適度なブス」は嫌われにくいです。
造形も雰囲気も美人じゃないけれど
他人が振り返って二度見するほどのブスでもない。
そして、自分を「普通」にカテゴライズしているのが、適度なブス。
最近、「普通」ってないなぁという考えになってきました。
美人か、ブスか。どっちか。
私は今、紛れもなくブス領域にいて、
それは、整形すれば解決されるということじゃなくて、
「私は美人♡」として生きるか、
「私は普通/ブス」として生きるか、
自分の心持ち次第というか。
これまで、
美に比重を置いている人に対して
すごい対抗心を持ってたなぁと思います。
これは子ども時代に培われてしまった偏見だと思うんだけど、
何もしなくても顔の造形が可愛い子や、派手な子がクラスで人気者だったりすると
「私はこんなに頑張って勉強でも習い事や部活でも結果を出しているのに・・!努力しないで人気者だなんてズルい!」
って、なんとなく思っていた気がします。
1番この思いが表出したのが大学受験のとき。
同じ学部の受験生の中に、
スタイル抜群で、スカートが膝上20cmで、顔も美人で、メイクばっちり、サラサラの髪をなびかせて、ピアスをした、キラキラ笑っている子がいたんですよ。
私は八戸から新幹線で3時間かけて東京に来て、周りを見上げながら看板を頼りに何とかキャンパスにたどり着いて、
膝下丈のスカートを履いてもちろんメイクもしない、黒髪のショートカットでしっかり横の髪を耳にかけた地方の優等生ルックで、
受験のストレスで顔面蒼白になりながらそこにいました。
そのキラキラした子を見て思ったこと。
「何なのあの子!あの子が受かって私が落ちるわけがない!!私はあの子がしてきた楽しみを全部犠牲にして、今まで受験勉強してきた!!」
結果、キラキラした子も、私も、合格しました。
まぁ、受かったから良かったんですけどね、
これで落ちていたら、もっと酷く歪んだ思いを持っていたかもしれません。
この無駄な対抗心・・!
自分に自信がなくて、努力を重ねて自信を外側(受験で言うと偏差値など)に求めていたので
いつまでたっても自己肯定できない、そして努力はつらいもの、
というのが当時の私でした。
そんな時期を経て、会社で同僚に「ブス」って言われて傷ついた時期も過ぎ去り、色々と考えを巡らせた結果、
「地味で適度なブス」として生きるのを
もうやめようと思って。
私も憧れている女性たちのように、
キラキラした美人になる!!!
ので、
「私は美人♡」
と思って生きていきたいと思います!
私の名前、本名の漢字は「美華」です。
美しく、華やか。
タナカミカ、華やか計画を始動しよう、そうしよう。
自分の名前を説明するとき、恥ずかしくて、わざわざ、
「ミカのカは中華料理の華です!」
などと言っていたのですが!
まずはそれをやめようと思いまーす。笑
「美しく華やかと書いて美華です♡」が
似合う女になりますー( ´ ▽ ` )!!!